令和6年度 部員作品集






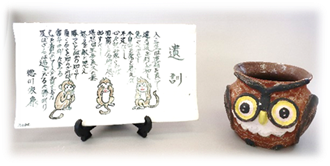



活動概要
活動日 毎週日曜 午後1時~午後5時
活動場所 東金市山田 起山窯(みきの湯隣)
会費 月2回参加 3,500円
毎週参加 7,000円
※その他作品に応じた焼成代を別途いただいております。
◆関東近県の窯場の見学会なども行っております。
興味がある方はぜひ倶楽部開催日に見学にお出でください。
そしてあなただけの一品を私たちと一緒に作りましょう。








